家庭用All-in-One蓄電池システム


SDGs×Murata
INDEX
グループ全体の気候変動対策を推進するうえで、工場が国内外にわたる場合、工場ごとの方針や地政学的な事情に左右され、意思統一が図りづらいケースも存在します。
そうした中で、ムラタでは気候変動対策を全社的に推し進め、再生可能エネルギー化を促進する社内制度として、投資回収年数の緩和と社内カーボンプライシングを採用しています。
勝間「省エネ効果などが期待できる高機能な設備を新設・増設する際、投資回収基準年数を緩和しました。例えば、年間の電気代が今より10万円削減できるエアコンを増設するとします。投資回収年数が5年の場合、10万円×5年=50万円の増設費用であれば投資を回収できます。同じ考えで、投資回収年数が10年の場合は、100万円を投資にあてることができます。投資回収年数の緩和によって、より高機能な省エネ設備に投資しようという促進効果が生まれるのです」

藤原「さらに、コスト削減にはつながらないけれど、CO2削減には効果がある設備を導入する場合、CO2の1トンあたりにバーチャルな価格を付け、CO2削減につながる投資を促進する社内カーボンプライシング制度を採用しています」

勝間「そのほかにも、2022年から『サステナビリティ投資促進制度』をスタートさせます。具体的には、環境投資を実行しやすい管理会計制度の導入、カーボンプライシング制度の適用範囲拡大などを行う予定で、今後も環境投資を促す制度づくりに努めていきます」
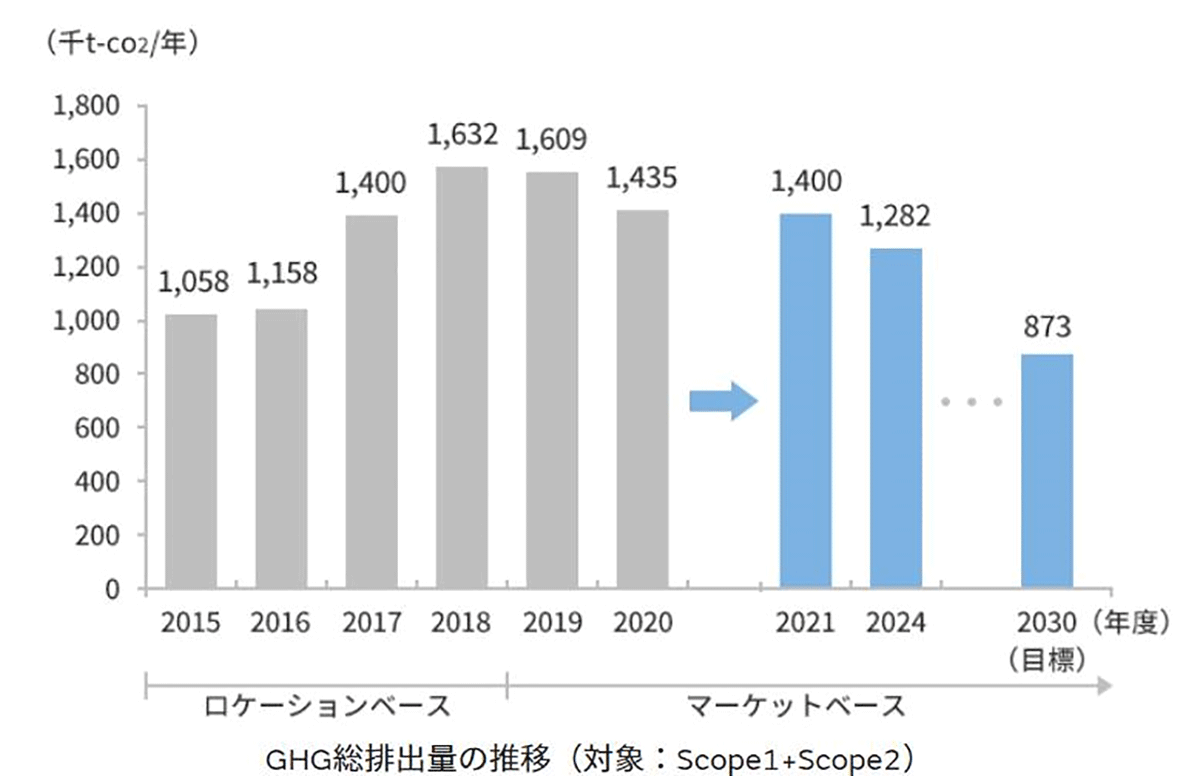
気候変動対策が企業の最重要課題になる一方で、工場ごとの事情によってプロジェクトが円滑に進まないケース、旗振り役となるトップの意思、さらには意思決定スピードに課題が存在するケースも多く見られます。ファシリティ部においてもそうした課題を共有しつつ、社内風土や課題解決への努力が重要だと言います。
藤原「気候変動対策に取り組むにあたって、経営判断や意思決定スピードが速いこと、そして、個人や各部に裁量が委ねられていることは非常に重要だと思います。例えば、私が気候変動対策に関する事例を調べて、ムラタがやるべきことを立案し、上司に提案する。それを聞き入れてもらえて、スピーディーに具現化していく。ムラタが目指す“自律分散型の組織”が根付いているからこそ、積極的に気候変動対策に取り組める環境が整っていると思います」
勝間「“自律分散型の精神”や、まずは失敗を恐れずにやってみよう、やってみて改良していこうという姿勢はムラタらしさだと感じています」
藤原「私自身は、それぞれの工場の状況や課題に対してまだ理解が及ばない部分があるので、しっかりと各工場の所管にヒアリングすること、独りよがりなコミュニケーションをとらないように心がけています」
勝間「岡山のメガソーラーは私が担当したのですが、全社方針を伝えながらも工場個別の事情や仕様要件があり、それらをしっかりとヒアリングし、調整することの大切さを実感しました。中国やフィリピンの工場でも自発的に気候変動対策のプロジェクトを立ち上げていて、同様に強い想いや考えがある。工場にも“自律分散型の精神”が根付いているのだと思います」
こうしたムラタの取り組みは外部評価機関からも高く評価され、2021年には国際的な環境非営利団体CDPによる「CDP Climate」にて、最高評価であるAリスト*に選定されました。
*評価結果は最上位レベルのリーダーシップレベル(A、A-)からマネジメントレベル(B、B-)、認識レベル(C、C-)、情報開示レベル(D、D-)の8段階で評価)。
勝間「評価機関から高く評価されている理由としては、ムラタが掲げる気候変動対策の目標設定、RE100やSBT認定などのイニシアティブ対応、取締役会やCSR統括委員会の審議を行うガバナンス面、そして“全社横断”で気候変動対策に取り組んでいることなどが挙げられます。“全社横断”は、まさに金津村田製作所の事例に当てはまると思います」
藤原「外部から高い評価を得る一方、SDGsや気候変動対策を社内に浸透させるという点では課題も感じています。社員一人ひとりが気候変動対策を含めた社会課題を自分ごと化し、社会をより良くするという意識に基づいた行動をとらなければ、ムラタの成長戦略である社会価値と経済価値の好循環を生み出すことはできないと考えています。今後も丁寧にこの課題に取り組んでいきたいと思います」