“工場力強化の達人”に聞く、保全業務のカン・コツ依存をいかに脱却するか?(後編)――保全のIoT化をスモールスタートで始める意義とは
工場設備の修理などを担当する保全業務は、保全担当者の経験や知識といった「カン・コツ」に依存する傾向が強い業務。そんなカン・コツ依存から脱却し、保全業務を標準化するためのカギとなるIoTですが、これまでIoTを導入したことがない企業や工場は、どのように導入を進めれば良いのでしょうか。前編に引き続き、“工場力強化の達人”と呼ばれるジェムコ日本経営のコンサルタント古谷賢一氏に話を伺いました。
少しでも早くデータ収集を開始することが、保全のIoT化成功のポイント
――前編では、IoTを活用した保全業務の可能性を伺いました。実際に今、IoTを導入する企業や工場は増えているのでしょうか。
IoT活用は保全分野でもフロンティアな領域であり、導入する工場は増えています。保全をサポートするIoTツール自体の数も多くなりました。たとえば、工場設備の駆動部分、モーターなどにセンサをつけて振動をモニタリングするツールなどが分かりやすい例です。さらに、振動をそのまま計測するだけでなく、周波数分解などのデータ処理を行いながら、異常を検知すればコンピュータがアラームを鳴らすようなシステムもあります。これらは前編でお話した「予知保全」を目的としたものですね。
もっと初歩的なIoTもあります。たとえば、設備どうしが互いに通信で連携していて、ひとつの設備に不具合が起きたら、次の工程の設備も自動的に停止するようなもの。これは、故障が起きてから対応する「事後保全」に位置付けられるものですが、迅速に故障に気づけるので、その後の工程への影響を最小限に抑えられます。もし故障に気づくのが10秒遅れたら、さらにその先の工程の機械まで故障させるかもしれません。
ほかにも、ある部品をアームでつかむ機械があったとして、何らかの理由でその部品をつかみ損ねたときに、ラインが自動で停止するような仕組み。本来流れるべきではない部品がラインを流れると、その先の設備にダメージを与えてしまうかもしれないので、その先の事故・故障を予防するという「予防保全」もよくある例です。
――IoTを活用することで、保全マンのカン・コツに依存していた業務をより標準化できる可能性もあるのでしょうか?
そうですね。特に設備のデータをモニタリングするような予防保全や予知保全には、大きな可能性があると思います。また、これまでIoT導入の経験がない企業や工場が導入を行うときに重要なのが、スモールスタートかつフレキシブルに導入を進めること。
いきなり工場全体にIoTを導入しても、うまくいかないようなケースも考えられます。そこで、まずは部分的に導入してみたり、モデルラインやモデル設備を設定したり、限定的な形でIoTを導入してみるのが得策です。もちろん、工場全体のあるべき姿を描いておくことは前提ですが、まずは部分的かつスモールスタートで始めて、ノウハウをつかんだら導入の範囲を広げていくといいでしょう。
――スモールスタートなら、時間もかけずスピーディな導入もできそうですね。
導入までのスピード感はとても大事です。なぜならIoTを活用した保全は、より多くのデータを収集し蓄積しなければ、なかなか本領を発揮できないからです。IoTを設備が停止したことを知らせる事後保全に活用するならば、すぐに効果を発揮するでしょうが、予防保全や予知保全の場合は、得られたデータを分析し技術的な評価を加えなければなりません。
IoTの保全ツールは増え、それを導入する工場も増えていますが、実はまだ「どこにセンサを設置すれば効果的か?」「どんなデータを取得すれば、故障を予知できるか?」、あるいは「データは得られたけれど、どう分析して良いか分からない」など、詳細なノウハウまで完璧に確立しているところは多くありません。IoTを活用した保全の“最適解”はまだ誰も分からないような状況です。
そこで重要になってくるのは、少しでも多くのデータを収集し、最適なやり方を社内で議論していくこと。ファクトベースの正確な議論を行うためにも、材料となるデータは少しでも多いに越したことはありません。
――データを少しでも多く集めておくためにも、スモールスタートは効果的なのですね。
はい。設備のクリティカルな故障というのは、それほど頻繁に起きるものではないと思います。となると、どんな挙動をしたらどんな故障につながるのか、その傾向を正確に把握するためにも、早くからデータを収集しておくことが大事なのです。
しかも先ほど言ったように、どの設備にどのセンサをつけ、どんなデータを取れば故障を予知できるのかといった最適解は、まだ誰も答えを持っていないような状況です。となると、いち早くそのノウハウを確立した企業や工場は、競争力という点でも優位に立てる。将来的な自社の発展につなげるためにも、スモールスタートは有効な手段だと言えるのです。そのとき、もうひとつ重要になってくるのが、収集したデータを分析することです。
これからの保全は現場主義にデータ主義が加わる?

――データ分析というのは、今までの保全業務にはあまりなかった領域かもしれません。
IoTを活用した保全業務の大きな特徴だと言えます。IoTは、これまでのカン・コツに依拠した現場主義の保全業務から、データに依拠した現場主義への変化をもたらすかもしれません。こうした変化は、保全のクオリティも大きく引き上げるでしょう。つまり今までの保全業務は、限られた担当者が現場で対応していたわけですが、データを細かく分析するデータサイエンティストのような人材も巻き込んだ形での、新しい保全のあり方が求められるということです。
そのために、収集したデータを正確に分析できる人材の確保が重要になってきますが、そうした人材と現場の保全担当者がいかに連携するかも大切です。そうした社内連携を取るためには、上層にいる人たちも保全の重要性をあらためて認識し、その価値を会社全体として再定義することが求められます。
――IoTを導入することと同じくらい、そこで得たデータを分析する作業が重要になりそうですね。
IoTを活用してデータをたっぷり貯め込んでも、それを生かすことができなければ、宝の持ち腐れです。たとえばモーターの振動データを取ったとしても、単にそれだけだと故障前後の振動の違いがよく分からない場合もあるでしょう。見た瞬間に判別できる明快な違いは、保全担当者が目視で確認しても気づくことができます。
振動をモニタリングしながら、それらを周波数分解する、あるいはさまざまな要素を細かく切り出してみる。そのようにして「この挙動は故障の前兆だ」というファクトをどこまで正確につかめるか。データを解析する能力が求められます。もちろん、実際の現場を知り抜いている保全担当者の知識やノウハウをそこにフィードバックしていくことも欠かせません。
つまりIoTは“ハードウェア”ですが、そこから得られたデータをどう分析し、どんなノウハウを確立するかという“ソフトウェア”の部分もきわめて重要になってくるということです。導入して終わりではなく、日々の保全業務におけるノウハウや気づきと、収集したデータを照らし合わせるより実際的な「分析」ができてからが本番。スモールスタートでいち早く導入して少しでもデータを貯めておくべきという提言は、こうしたことにもつながります。
――最後に、IoTの導入を進める中で、人的リソース面での保全担当者の育成はどうするべきでしょうか。
もちろん、保全担当者の技術伝承も並行して行う必要があります。IoTか人か、決してどちらかを選ぶような話ではありません。これから労働人口は減っていきますし、新型コロナウイルスの影響で仕事の遠隔化も進んでいます。保全業務もその例外ではありません。先輩保全担当者が若手と一緒に現場で作業をしながらノウハウを伝えていた従来のやり方が、遠隔からの指導や教育に取って代わるかもしれません。
ただでさえ「暗黙知」的なものを伝えるのに苦労していたのに、そうなるとこれまで以上に保全担当者の育成には時間がかかるでしょう。遠隔での指導には限界がありますし、細かな作業やニュアンスなど、現場で一緒に教えてもらわないと分かりにくい点も多いはずです。今までよりも、保全担当者の技術伝承は難しくなり、育成にリソースを割かなければならない必要性が出てきます。
データを取って分析することは大事ですが、その先の保全の実作業は人の手に委ねられます。ですから、現場で手を動かす保全担当者の育成は、今後も依然として重要度は高い。
そこで大切になってくるのが、前編でもお話した保全業務の一つひとつを細かく洗い出し、形式知化するためのプロセスなのです。これはIoTを導入する上でも、保全マンの育成においても共通する、すべての土台となる基本的な作業です。IoTの導入を検討する際には、洗い出した作業のどの部分にIoTを入れるべきか、またどこのデータを取れば有効かを考える手立てになります。人材の育成においては、一つひとつの作業を言語化することで、より分かりやすくノウハウを教えられます。
IoT導入と保全担当者の育成、どちらを成功させる上でも、まずはこうした土台の部分からしっかり考えていくことが、やはり重要だと言えるのです。
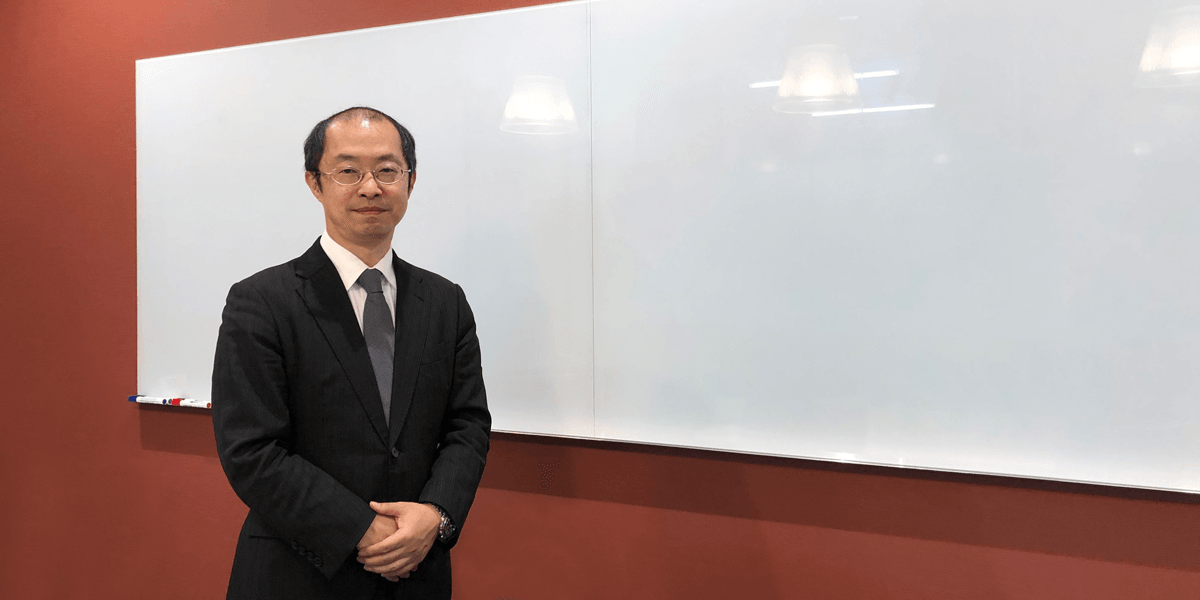
古谷賢一(ふるたに・けんいち)
株式会社ジェムコ日本経営 本部長コンサルタント。数多くの製造現場へのコンサルティングを筆頭に、経営管理や人材育成、品質改善支援、ものづくり革新支援など幅広い分野に従事。海外工場の支援実績も多い。ものづくりの現場に密着した、きめ細かなコンサルティングは多くのクライアントから高い評価を得ている。セミナーや講演、雑誌への寄稿実績も多数。
無線センシングソリューションは、無線センサにより工場設備等の状態を収集・可視化することで、点検作業の効率化や予知保全を実現します。無線センシングソリューションサイトでは現場改善のヒントや導入事例を掲載しています。保全業務にお悩みの方は是非ご覧ください。


