ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/ESD保護デバイス
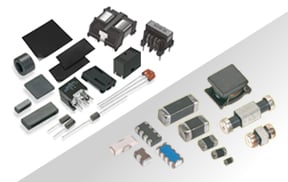
ノイズ対策ガイド
当コラムは、"チップフェライトビーズの誕生秘話(前編)"の続編です。
商品開発と並行して、「品名をどうしようか?」「日本語で何と呼ぼうか?」という議論が始まった。村田製作所の品名体系を調べて、いくつかの案を考えた。BL(ビーズ)は既に決まっていたが3文字目をどうするか、特性表記はどうするかが議論になった。品名はいくつかの案からBL+M(Multilayer)に決まり、BLM41A01(数年後品種が多くなってBLM41AG700と改名することになる)という品名に決まった。
一方、日本語名は、いい案が出ずなかなか決まらずにいた。数日後、部長が出勤してきて「日本語名は"チップソリッドインダクタ"でどうかな?」の一言で決まった。実は、日本語名も数年後に、欧米で使われていた現在の"チップビーズインダクタ"に改名することになるのであるが・・・。
商品設計審査も終わったので、課長が紹介資料を持ってお客様へのPR活動を始めた。資料で紹介しただけなのに、1週間後には某お客様からプリンターに使いたいとの一報が入った。さあ、そこからがまた大変である。
手元にあるのは八日市事業所に積層コンデンサ(GR)からもらってきた古い積層設備と外部電極塗布機のみである。特性選別機、テーピング機など影も形もなかったのである。さあ、どうしよう。営業担当者を通して、お客様がいつから何個/Week使われるのかを確認し、それを準備するために工場との調整が始まった。測定とテーピングは関連会社に測定器、エンボステープ、治工具を持ち込んでの手作業対応を頼みこんだ。確か、7000個/Weekぐらいだったと思うが、その程度の数量だったので何とか対応することが出来た。
それをきっかけに、部長が300万個/月体制をとるように号令をかけた。私としては「雲の上の夢のような数字で本当に売れるのだろうか?」「そんな数の量産設備を入れていいのか?」という感想しか出てこない、驚きの数字だった。八日市事業所の人と一緒に本社生産技術部門(野洲)へ行き、どのような特性を測定するのか、必要な測定項目の話をした。 その後、設備メーカーにも行って、ようやくBST(BLM測定テーピング機)1号機が八日市に導入されることになった。
BLMを納入して1ヶ月とたたずにクレームが来た。課長にお客様のところで問題があったようなので、明日一緒にお客様のところに行ってくれと言われた。はじめてのお客様への出張が、クレーム出張になったわけである。
廊下のようなところのパーテーションで区切った打合せ室に通されてクレームの内容を聞いた。その当時出てきた噴流フロー半田で実装し、電極喰われのクレームである。ここからが短期決戦の始まりである。
まずは、Ag/Pdを2回塗布(厚く形成)して、暫定対策を了承していただき、1ヶ月程度の猶予を頂いた。対策はめっき仕様に変更するしかないことはわかっていた。めっき検討をお願いするため関連会社を行き来する日々が続いた。その当時めっきにより電極強度が落ちると言われて、めっき対応の厚膜電極の開発が必要だと言われた。しかし、クレームなのでそんな時間はない。村田製作所内で使っている厚膜電極を10種類以上集めてすべて評価した。最終的に最も強度が高い厚膜電極に決め、顧客クレームに対応した。
このクレームによって、商品化から数カ月で外部電極仕様は、現在のAg厚膜+Ni/Snめっき仕様に変更になったのである。
このようにBLMシリーズを短期間に商品開発・量産対応できたのは、先に生まれていた積層コンデンサ(GRシリーズ)、チップコイル(LQHシリーズ)の担当者の協力、実装評価・めっきでの関係会社の協力、そして量産に向けた工場の協力があっからだと思う。
この時に知り合い、一緒に苦労した人達とは27年を経た今でも一緒に仕事をする機会を頂いている。楽しい商品開発と、それをとおしていろんな経験をさせて頂いたことを大変感謝している。
その後、アレイ商品(8,6,4素子)、信号周波数の高速化に対応したシリーズ展開等多くの品種が生み出されていき、大きな商品に成長していくことになったのは、また次のお話で...(お楽しみに)
担当:村田製作所 EMI事業部 H.T.
記事の内容は、記事公開日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。